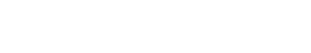国際社会科学専攻は、国際関係論コースと相関社会科学コースの2つのコースで構成され、広範な領域の社会科学について研究・教育を行っています。
国際関係論コースでは、現代社会の動態やその歴史および基盤を国際的視点から理解することを目的として、国際政治、比較政治、国際法、国際経済、国際経営、開発学、国際関係史といった諸分野を扱い、相関社会科学コースは、社会科学の基礎領域である、法、政治、経済、社会についての学問的知識を横断的にとらえ、現代の社会現象を哲学的・思想的な側面と実証的・計量的な側面の両方向から総合

的に解明することを目的としています。国際的分析・比較に軸足を置くか横断的な学問知を探求するかの重点の違いはあれど、両コースともに専門分化された既存の学問領域の枠組みにとらわれず、複雑な現代社会の動態を深くまた正確に理解することを目指す点において共通しており、両コースの教育は、国際社会科学専攻に所属する30名強の教員を中心として、他専攻・他研究科の教員や客員教員の協力も得て行われています。
当専攻が所在する駒場キャンパスは、渋谷から徒歩圏内にあるとは思えないほど緑豊かで、比較的こぢんまりとした構内で文理にわたる多様な専門分野の学生・研究者が活動しているためか、活気とリラックスした自由な空気が感ぜられます。当専攻にも多様な学問分野を専門とする教員・学生が集っており、日々の研究の合間の雑談は同じ専門内の者だけで話しているのとは異なる負荷と刺激に満ちています。同じ専門分野を志す者同士であればツーカーで通じる(ように思われる)事柄についても、隣接分野を専門とする研究者に対して納得が得られるように説明することは案外難しく、そうした経験を通じて、わかった気になっていたことについても実は新たな疑問や課題があることに気づかされ、あるいは自らの専門分野の方法論について改めて熟考させられることも多いでしょう。これまでの修了者は、大学・研究所、国際機関、官公庁、NGO、シンクタンクなど幅広い分野で活躍していますが、現在のそして将来の大学院生の皆さんにも、日々の研究と対話を経て修士論文・博士論文を完成させ、社会の変化に対応しうる深い専門知と分析力を備えた人として、学術的な成果を社会に還元していってほしいと期待しています。
専攻長 西村弓